スタッフブログ
2021年2月14日 日曜日
獣医師伊藤の自己紹介と"使用しない方がいい"飼い鳥の飼育グッズ
当ブログを見てくださっている皆さま、初めまして、去年の7月から勤務している獣医師の伊藤文人と申します。
自分は愛知県出身で、酪農学園大学を卒業し、関西の動物病院で勤務医をしたのち、もねペットクリニックにやってきました。
スキーや映画鑑賞が趣味で、北海道で学生をしていた時は、よく札幌周辺のスキー場へ通っていました。

名古屋近辺に住んでいると想像しにくいですが、札幌周辺には日帰りで行ける距離にスキー場が複数あって、
雪に縁のなかった学生もたいていスキー、スノボができるようになって卒業していきます。
以前勤めていた動物病院は、もねペットクリニックと同じくエキゾチックアニマルも含め幅広い動物種の診察を行う病院でした。
なかでも、エキゾチック担当の先生が鳥の専門病院に長年勤めていたこともあり、特に鳥類の診察件数が多く、
その先生から飼い鳥の診察について、専門病院で培われてきた多くの経験と知識を学ばせていただきました。
こういった経緯もあり、今回は当院のホームページで触れられていない
飼い鳥の"使用しない方がいい"飼育グッズについて軽くお話させていただこうと思います。
以下にそれらのグッズを紹介していきます。
塩土

赤土、塩、ボレー粉を石膏で固めて作られ、昔からミネラル補給、嘴のトリミング目的で使用されている副食です。
よく使用されている飼い主さんも見かけるのですが、最近では次の大きなデメリットから基本的に使わない方がいいとされています。
① 小石や砂の過剰摂取によって、砂嚢の逆流や胃腸が荒れるなどの消化器疾患の原因になる。
鳥には口から食べたものを砂礫ですりつぶして消化を助ける砂嚢という器官があります。
塩土に含まれる砂や小石が、その砂礫をためることに役立つとされています。
しかし皮を剝いて実を食べる多くのインコにとってはさほど砂礫は重要でないらしく、
むしろ食べ過ぎの結果、砂礫の逆流による嘔吐、結晶が粘膜を傷つけたり、胃腸がうまく動かなくなる、うっ滞などの原因になる事が多いです。
② 塩分の取りすぎ
人間もそうですが、塩分の取りすぎは腎臓への悪影響を及ぼす可能性があります。
③ カビなどの衛生面の問題
塩土の上にフンをしたりして不衛生で、湿った状態を放置すると塩土の表面にカビが生えることがあります。
そんなものをかじるのは明らかに健康によくないですが、
なによりカビの仲間は呼吸器や肝臓にかなりの悪影響を与える病気の原因になることも多いです。
サンドパーチ
小鳥の爪のケアを目的に止まり木の表面を砂などでコーティングしてあるものです。

初めからコーティングされた止まり木タイプや、今ある止まり木に巻いて使用するカバータイプのものがよく売られています。
鳥が爪を削る目的どおりに使用してくればいいのですが、猫のように自分で爪を研いでくれるわけもなく、
ただ足の裏を削るだけに終わるケースが多く、ひどいと皮膚炎などの原因になります。
さらに表面の砂をついばむ子も多く、塩土の時と同じく、その砂が胃炎や砂礫の逆流などの消化器疾患の原因になる可能性もあります。
このように時代によって正しいとされている飼い方は変化していきますし、
市販されているからといって必ずしもペットにとって有益なばかりのものとは限らないケースもあります。
日々、情報の更新を心がけていきたいですね。

にほんブログ村
自分は愛知県出身で、酪農学園大学を卒業し、関西の動物病院で勤務医をしたのち、もねペットクリニックにやってきました。
スキーや映画鑑賞が趣味で、北海道で学生をしていた時は、よく札幌周辺のスキー場へ通っていました。

名古屋近辺に住んでいると想像しにくいですが、札幌周辺には日帰りで行ける距離にスキー場が複数あって、
雪に縁のなかった学生もたいていスキー、スノボができるようになって卒業していきます。
以前勤めていた動物病院は、もねペットクリニックと同じくエキゾチックアニマルも含め幅広い動物種の診察を行う病院でした。
なかでも、エキゾチック担当の先生が鳥の専門病院に長年勤めていたこともあり、特に鳥類の診察件数が多く、
その先生から飼い鳥の診察について、専門病院で培われてきた多くの経験と知識を学ばせていただきました。
こういった経緯もあり、今回は当院のホームページで触れられていない
飼い鳥の"使用しない方がいい"飼育グッズについて軽くお話させていただこうと思います。
以下にそれらのグッズを紹介していきます。
塩土

赤土、塩、ボレー粉を石膏で固めて作られ、昔からミネラル補給、嘴のトリミング目的で使用されている副食です。
よく使用されている飼い主さんも見かけるのですが、最近では次の大きなデメリットから基本的に使わない方がいいとされています。
① 小石や砂の過剰摂取によって、砂嚢の逆流や胃腸が荒れるなどの消化器疾患の原因になる。
鳥には口から食べたものを砂礫ですりつぶして消化を助ける砂嚢という器官があります。
塩土に含まれる砂や小石が、その砂礫をためることに役立つとされています。
しかし皮を剝いて実を食べる多くのインコにとってはさほど砂礫は重要でないらしく、
むしろ食べ過ぎの結果、砂礫の逆流による嘔吐、結晶が粘膜を傷つけたり、胃腸がうまく動かなくなる、うっ滞などの原因になる事が多いです。
② 塩分の取りすぎ
人間もそうですが、塩分の取りすぎは腎臓への悪影響を及ぼす可能性があります。
③ カビなどの衛生面の問題
塩土の上にフンをしたりして不衛生で、湿った状態を放置すると塩土の表面にカビが生えることがあります。
そんなものをかじるのは明らかに健康によくないですが、
なによりカビの仲間は呼吸器や肝臓にかなりの悪影響を与える病気の原因になることも多いです。
サンドパーチ
小鳥の爪のケアを目的に止まり木の表面を砂などでコーティングしてあるものです。

初めからコーティングされた止まり木タイプや、今ある止まり木に巻いて使用するカバータイプのものがよく売られています。
鳥が爪を削る目的どおりに使用してくればいいのですが、猫のように自分で爪を研いでくれるわけもなく、
ただ足の裏を削るだけに終わるケースが多く、ひどいと皮膚炎などの原因になります。
さらに表面の砂をついばむ子も多く、塩土の時と同じく、その砂が胃炎や砂礫の逆流などの消化器疾患の原因になる可能性もあります。
このように時代によって正しいとされている飼い方は変化していきますし、
市販されているからといって必ずしもペットにとって有益なばかりのものとは限らないケースもあります。
日々、情報の更新を心がけていきたいですね。
にほんブログ村
投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL
2021年2月 2日 火曜日
獣医師平林の小話 ~ヘビダニ~
お久しぶりです。獣医師の平林です。
最近少し暖かくなってきたと思ったら、また寒くなってきて雪まで降ってきましたね。
青森県の大学に行っていたので雪を見るのは好きですし、心が落ち着く光景ではあるのですが、道路がひどく混雑するのだけは参ってしまいますね。
さて、今日のお話ですが、爬虫類の外部寄生虫の症例をご紹介させて頂こうと思います。
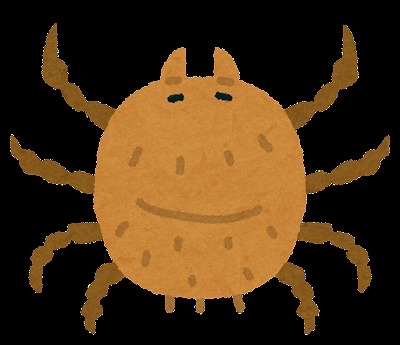
実は爬虫類の皮膚疾患、そして今回ご紹介することは出来ませんが消化器疾患、というのはとても来院数が多い分野になります。
そもそも犬猫の場合でも皮膚や消化器というのは来院理由の大部分を占める分野になります。
エキゾチックアニマルの場合はそれに加えて、「小動物は毎日一緒にいるご家族でも体調不良に気付きにくい」というなかでも食欲・排泄・体表面の不調というのは比較的気付いてあげやすいというのも理由かもしれません。
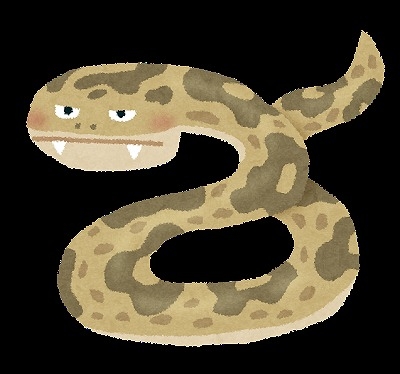
爬虫類の皮膚疾患としては脱皮不全、皮下膿瘍、低温火傷、感染症などなど紹介しきれないくらいあります。
その中でも今回お話するヘビダニについては、ある日突然なる病気、というよりお迎えの時に気を付けて欲しい病気になります。
ヘビに限らず爬虫類のダニというのははポピュラーな病気ではありますが、ちょっとだけ気を付けなければならない買い方、というのがあります。
即売会等のイベントです。

単純に全国各地のショップ、多種多様な生体が密集する空間でもありますし、移動のストレスで生体の免疫力が落ちている状況でもあります。
イベントは非常に楽しい空間ですし、僕自身も新しい子のお迎えを目的に参加したことがありますが、やはり店舗での購入よりもお迎え時からの体調不良で来院されるケースは多いように感じます。
とはいえ最近はコロナでそもそもイベントが自粛傾向ですので、今はあまり関係がなかったかもしれませんね。
さて、ではここからは実際の症例の写真をご紹介させて頂きます。
こちらは生後半年のデザイナーズカーペットパイソンさんです。

ベビーのヘビさんをお迎えしたところダニが付いていたようで、家の子全員にダニが移ってしまったとのことで、この子が代表して来院されました。

ヘビダニは鱗の隙間なんかによくいたりするのですが、色合いが黒っぽい子であること、ピントがうまく合わなかったことから良い写真が撮れませんでした。
ペットシーツに落ちていたダニ。こちらはとても見やすいですね。

こちらはダニをつぶしたところになります。
赤くなっていることから吸血しているというのが良く分かりますね。

治療法としては飲み薬での駆虫はもちろんのこと、家にいる子全員が治療をすること、飼育環境の清浄化(ケージ内の駆虫)、が必須になってきます。
ダニなどの外部寄生虫による皮膚炎は、不快感としてはかなり強い部類になるので早めに治療してあげたいですね。
お迎えした子は基本的には1ヶ月程度は先住の子とは隔離して飼育して頂いて、問題がないのが分かってから、もしくは健康診断を受けてから、一緒にして頂くと良いですね。
爬虫類に限らず、この記事を読んでつい自宅の子の皮膚チェックをしてしまった、という方は↓クリック↓して頂けるとありがたいです。
最近少し暖かくなってきたと思ったら、また寒くなってきて雪まで降ってきましたね。
青森県の大学に行っていたので雪を見るのは好きですし、心が落ち着く光景ではあるのですが、道路がひどく混雑するのだけは参ってしまいますね。
さて、今日のお話ですが、爬虫類の外部寄生虫の症例をご紹介させて頂こうと思います。
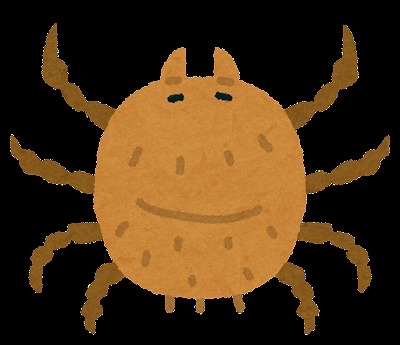
実は爬虫類の皮膚疾患、そして今回ご紹介することは出来ませんが消化器疾患、というのはとても来院数が多い分野になります。
そもそも犬猫の場合でも皮膚や消化器というのは来院理由の大部分を占める分野になります。
エキゾチックアニマルの場合はそれに加えて、「小動物は毎日一緒にいるご家族でも体調不良に気付きにくい」というなかでも食欲・排泄・体表面の不調というのは比較的気付いてあげやすいというのも理由かもしれません。
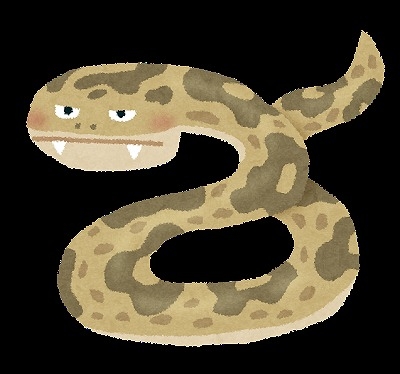
爬虫類の皮膚疾患としては脱皮不全、皮下膿瘍、低温火傷、感染症などなど紹介しきれないくらいあります。
その中でも今回お話するヘビダニについては、ある日突然なる病気、というよりお迎えの時に気を付けて欲しい病気になります。
ヘビに限らず爬虫類のダニというのははポピュラーな病気ではありますが、ちょっとだけ気を付けなければならない買い方、というのがあります。
即売会等のイベントです。

単純に全国各地のショップ、多種多様な生体が密集する空間でもありますし、移動のストレスで生体の免疫力が落ちている状況でもあります。
イベントは非常に楽しい空間ですし、僕自身も新しい子のお迎えを目的に参加したことがありますが、やはり店舗での購入よりもお迎え時からの体調不良で来院されるケースは多いように感じます。
とはいえ最近はコロナでそもそもイベントが自粛傾向ですので、今はあまり関係がなかったかもしれませんね。
さて、ではここからは実際の症例の写真をご紹介させて頂きます。
こちらは生後半年のデザイナーズカーペットパイソンさんです。

ベビーのヘビさんをお迎えしたところダニが付いていたようで、家の子全員にダニが移ってしまったとのことで、この子が代表して来院されました。

ヘビダニは鱗の隙間なんかによくいたりするのですが、色合いが黒っぽい子であること、ピントがうまく合わなかったことから良い写真が撮れませんでした。
ペットシーツに落ちていたダニ。こちらはとても見やすいですね。

こちらはダニをつぶしたところになります。
赤くなっていることから吸血しているというのが良く分かりますね。

治療法としては飲み薬での駆虫はもちろんのこと、家にいる子全員が治療をすること、飼育環境の清浄化(ケージ内の駆虫)、が必須になってきます。
ダニなどの外部寄生虫による皮膚炎は、不快感としてはかなり強い部類になるので早めに治療してあげたいですね。
お迎えした子は基本的には1ヶ月程度は先住の子とは隔離して飼育して頂いて、問題がないのが分かってから、もしくは健康診断を受けてから、一緒にして頂くと良いですね。
爬虫類に限らず、この記事を読んでつい自宅の子の皮膚チェックをしてしまった、という方は↓クリック↓して頂けるとありがたいです。
投稿者 ブログ担当スタッフ | 記事URL



































