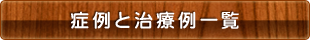※このページでは、アカハライモリについて紹介しています。

イモリの飼い方・健康管理の紹介


HPをご覧のみなさまへ
全国から電話でのお問い合わせがありますが、当院では「電話・FAX」での「飼育相談・診療相談(遠隔治療)」は行っておりません。
※診察対象のお問合せ、初診での受付内容(受付時間・持込方法など)、獣医師の不在確認、手術の予約、他の病院からの紹介状による相談は、診察時間内にお願いいたします。
分類学

両生類網有尾目イモリ亜科イモリ科、20属に分けられます。
北アメリカ大陸、地中海沿岸、日本を含む東アジア、ヨーロッパに分布します。
河川、池沼などに生息し、一般的に飼育されている種として日本固有種としてアカハライモリがあります。
特徴

アカハライモリは、全長おおよそ 10㎝前後、2 対の足と長い尾、腹側が赤色に黒のまだら模様が一般的です。
皮膚よりテトロドキシンと呼ばれるフグ毒と同じ成分を分泌します。
また、変温動物です。(外気温の影響あります。)
アカハライモリは他の種に比べ、気温変化に強く、食欲旺盛です。
両生類の為、幼体から成体へ変態を行います。
そのため呼吸様式がエラ呼吸から肺呼吸に変化していきます。
生息地は生まれたばかりでは水中のみですが、成体は繁殖期を除き、水辺の木の葉の裏などの陸上で生活します。
3 ~ 5年で成熟し、気温が上がり始める春になると繁殖のシーズンを迎えます。
寿命は、約20~25年といわれています。
一般的な飼育環境
1ケージに1頭の単独飼育を推奨します。ケージ内に過密になると共食いや皮膚毒の影響があります。
28度以上の高温には弱く、寒さには強いですが10℃以下の低温になると冬眠に入ってしまうため、注意が必要です。
飼育ケージ

30㎝ほどのプラケースもしくは水槽を選びます。
壁を上って脱走するため、厳重な対策が必要です。
ケージ環境
●水温
最適温度は20℃前後です。高温(30℃以上)になると命の危険あり、低温(10℃以下)になると冬眠します。
暑さに弱く、寒すぎると冬眠に入る為、冷却クーラーや簡易扇風機や、保温の為にパネルヒーターなどが必要な場合もあります。
●水量
ケージに合わせた適切な量を入れます。(水量が多ければ水質の汚染はされにくいです。)
●陸地
成体になると肺呼吸に変わるため、陸地が必要となります。
石や砂利、木などを使い、隠れ家のイメージで設置すると良いでしょう。
●水草
体を隠したり、繁殖の際に卵を産み付けたりするために必要です。
●ろ過機
水質を良い状態で保つことに役立ちます。
飼育ケージが大きくなる場合は必須となります。
ただし、水流はあまり強くしないようにします。
●水の交換
清潔な水を必要とするため、カルキ抜きをした水にて 1 ~ 2週間程度で交換します。
(ろ過機など導入する際には交換する間隔は伸ばすことが可能です。)
食事について
肉食であり、野生ではオタマジャクシやミミズ、虫、小魚を食べています。
そのため、乾燥アカムシやイトミミズ、メダカなどの生餌。
または、カメの餌などの人口餌などを与えます。
アカハライモリは食欲が旺盛で与えられた分だけ食べてしまうため、食べ過ぎによる肥満や消化不良になりやすいです。
食餌の回数は水質のことも考えると週 1 ~ 2 回程度、量はお腹の張りを見つつ調節して与えてください。



健康管理及び・治療の紹介
当院では、イモリの健康診断として、
・全身状態を確認する為の「視診」
を主に行っています。
当院で治療件数が多い症状・疾患は、
・浮遊病
・外傷
・脱皮不全
です。
※詳しくは「症例と治療例の一覧」をご覧ください。